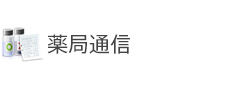1.どうして副作用が起こるのでしょう?
抗がん剤は細胞そのものを傷つけたり、分裂を邪魔したりして細胞を殺す作用を持っています。
がん細胞だけじゃなく正常細胞にも効いてしまうので、副作用が起こります。
2.影響を受けやすい部位、症状は?
・・・分裂、増殖が盛んな細胞です。
a) 血液をつくる骨髄の中にある造血幹細胞 → 造血幹細胞が壊される → 骨髄抑制 → 白血球の減少 → 免疫力低下 → 感染症にかかりやすくなります。
b) 胃腸の粘膜 → 粘膜細胞が壊される → 吐き気や嘔吐、下痢や便秘などの症状が出ます。
c) 口の粘膜細胞 → 粘膜細胞が壊される → 口内炎
d) 神経細胞 → 神経細胞の突起部の微小管が壊される → 神経細胞へ栄養が届かなくなる → 末梢神経障害を引き起こします。
e) 肺 … 発症機序は不明だが薬剤性急性肺障害、間質性肺炎などを引き起こす可能性があります。
脱毛も毛母細胞が障害を受けるからです。
この他、心臓、腎臓など、様々な臓器や器官に影響を及ぼすことがあります。

3.副作用の正しい理解
副作用の中で起こりやすいものは吐き気、嘔吐、脱毛、骨髄抑制です、ただ抗がん剤の種類により症状、程度は異なりますし、薬の反応も人によって違います。個人差が大きいです。
抗がん剤治療を受けるときは、副作用について主治医から説明を聞き、正しく理解しましょう。
(予測できる症状には、予防対策もたてられます。)
思い当たる症状が出た場合はすぐに医師や看護師に伝えられるので、副作用の早期発見、早期治療につながり、重症化を防ぐことができます。
白血球減少のように自覚症状のない副作用は、定期的に血液や尿の検査を受けることで発見できます。
副作用のほとんどは治療が終われば回復します、このことを覚えておき、過剰な不安をもたずに治療に望むことが大事です。